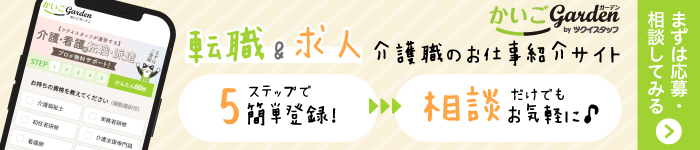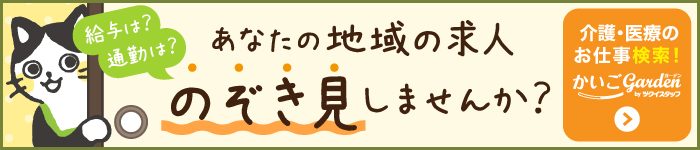薬を間違えて飲んでしまう誤薬、車椅子やベッドなどからの転落、転倒といった介護中の事故。100%ゼロにすることはできなくても、事故報告書を適切に活用することでリスクを減らし、施設の信頼性を高めて利用者様に安心して過ごしていただくことができます。
薬を間違えて飲んでしまう誤薬、車椅子やベッドなどからの転落、転倒といった介護中の事故。100%ゼロにすることはできなくても、事故報告書を適切に活用することでリスクを減らし、施設の信頼性を高めて利用者様に安心して過ごしていただくことができます。
事故報告書の様式は市町村によってバラバラでしたが、令和3年の審議で国によって統一され、標準様式が示されました。また、重大な事故が起きた場合は速やかに事故報告書を作成し、5日以内に原則電子メールで市町村に提出することとされました※。
今回のコラムではこのフォーマットに沿って記載例を挙げつつ、作成の流れやポイントをお伝えしていきます。事故報告書を上手に活用して、ぜひ安全・安心な介護につなげてくださいね。
事故報告書のフォーマット(様式)

今まで市町村によって異なるフォーマットが使われてきた事故報告書ですが、広く情報共有しやすくするため様式の統一が行われました。厚生労働省から示された標準様式は、下記からダウンロードすることができます。
≫事故報告書フォーマットのダウンロード(厚生労働省ホームページ)
一時報告の提出期限は5日以内
死亡事故や、医師の診断を受けて治療が必要となった場合、介護事業所は市町村へ報告する義務があります。その場合、第一報は事故発生から5日以内に行います。
それ以外の場合でも、事故が発生したら他の業務に優先して速やかに作成しましょう。具体的には下記のような流れになります。
- 介護中に事故が起こったら、ただちに救急車を呼ぶなど必要な緊急対応をとる
- できるだけ早くサービス責任者に報告を入れる
- 報告を受けた責任者は、その日のうちに家族、ケアマネジャーへ概要を報告。重大な事故だった場合、事故報告書の1~6項目を記入し、5日以内に市町村へ第一報を入れる
- 関係者が集まって事故の検証を行い、その内容をもとに事故報告書の7~9項目を記入し、家族や行政に追って報告を行う
- 事故報告書をもとにケアプランや業務の見直しに役立てる
その後の事故の検証は1週間以内を目安に。いったん報告書を書き上げた後も、家族への報告内容や、やりとりの経緯、その後どのような対応を行ったかを、そのつど事故報告書に追記していきましょう。
書き方のコツは「箇条書き」&「時系列」
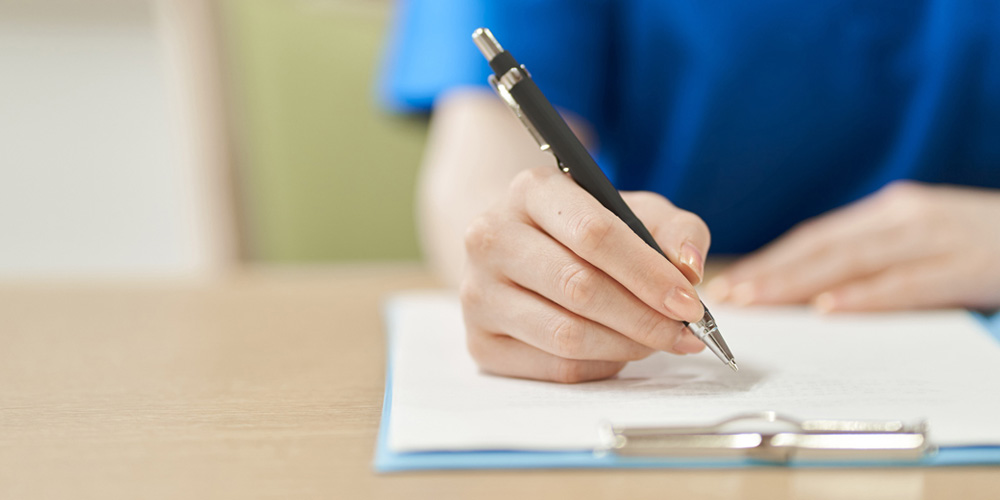
とくに事故報告書のなかの項目4「事故の概要」や5「事故発生時の対応」などは、誰が見ても分かりやすく、客観的に書く必要があります。
コツは時系列で(物事が起こった順に)、箇条書きにしていくこと。5W1Hも良いですが、「いつ・どこで」はチェック項目がありますので、「誰が・何を・なぜ・どうした」をとくに意識するとよいでしょう。はっきり特定できない場合や推定の場合は、文末に「(推定)」と書き添えておきましょう。
また項目7「事故の原因分析」は、スタッフの人為的なミス、設備の不良、利用者側の要因など、いくつかの角度から探るようにします。以下でケース別に例を挙げていきますので、参考にしてくださいね。
介護事故のケース別記載例
1.転落、転倒
- 発生時状況、事故内容の詳細
・ベッドから車椅子に移乗介助をするにあたり、「車椅子に移りますよ」と声かけをしたところ○○さまから「はい」と返答があった
・移乗中利用者の体重を支えきれず、車椅子への座り方が浅すぎたため前のめりに転倒
・転倒後、意識ははっきりしていたが、足の付け根に痛みを訴えられた - 発生時の対応
・応援を呼び、ただちに受診(担当者名、時刻) - 事故の原因分析
・大柄な利用者を小柄な職員一人で介助していた
・移乗時、ベッドと車椅子の間に10センチ程度の距離があった
・事前の声かけが不十分で、利用者をうまく誘導できていなかった - 再発防止策
・大柄な利用者を介助する場合、職員2人体制で介助する
・ベッドと車椅子の位置関係を確認することを徹底する
・事前に利用者にも、具体的にどのような手順で移乗するかを説明しておく
2.誤薬
- 発生時状況、事故内容の詳細
・夕食後に飲むべき薬(○○)を間違えて、朝食後に飲ませてしまった - 発生時の対応
・薬を飲んだ直後に気付き、医療職へ報告、バイタルを測定。体温:○℃、血圧:○○、脈拍○○・・・(担当者名、時刻)
・見守りを頻回にするよう申し送り(担当者名、時刻) - 利用者の状況
・30分後のバイタル:体温:○℃、血圧:○○、脈拍○○・・・
・気分は悪くないかを確認、「大丈夫」と回答あり(担当者名、時刻) - 事故の原因分析
・通常は担当者が仕分けをした後、別の職員が1.○○○○、2.○○○○の手順でチェックを行っているが、1の手順が守られていなかった
・2の手順の時にも名前の確認だけで、朝食後なのか夕食後なのかまではチェックしていなかった - 再発防止策
・手順1と2を再確認し、担当者の判断で省略することがないように徹底する
・名前以外にも、朝食後か夕食後かなど、飲むタイミングについても確認を行う
3.むせこみ、誤嚥
- 発生時状況、事故内容の詳細
・夕食の食事介助中に、2センチ大のジャガイモの煮物を介助し、飲み込みを確認
・その後他の利用者に呼ばれたために30秒ほど目を離したところ、激しいむせこみがあった - 発生時の対応
・背中をさすりながら「○○さん、しっかり咳をして、出してください」と声をかけ続けた(○○秒程度)
・医療職(担当者名)へ報告(時刻)
・栄養士(担当者名)、調理スタッフ(担当者名)に報告(時刻) - 利用者の状況
・むせこみが落ち着いた後、気分は悪くないかを確認、「大丈夫」との回答あり(時刻)
・意識ははっきりしていたが、食欲はなく、やや疲れた様子
・○時○分の見回り時、特段の変化なくお休み - 事故の原因分析
・一瞬目を離したすきに、自分で食べたものが気管に入り、むせたと考えられる - 再発防止策
・栄養士と相談し、食事の形態を変更して様子を見る
・食事中は嚥下に不安のある利用者から目を離さないようにする
・他の利用者に呼ばれた場合は別の職員が対応できるよう、事前に連携しておく
4.物損事故
とくに訪問介護で件数の多い事故が、掃除中に棚のものを落として壊してしまうなどの物損事故。本人や家族に「気にしないで」と言われたとしても、きちんと文書で報告をします。
- 発生時状況・事故内容の詳細
・利用者宅で昼食後の食器洗い中、利用者から「○○さん」と声をかけられた
・手に持っていた白い直径20センチ大の皿を落として割ってしまった - 発生時の対応
・利用者に報告(時刻)
・破片の片付け(時刻) - 事故の原因分析
・利用者に声をかけられたため、急いで洗い物を終わらせようとした
・作業スペースが狭く、作業がしづらかった - 再発防止策
・作業中に声をかけられた際は、いったん作業を中断して対応する
・作業前にできるだけ片付け、スペースを確保する
事故報告書のNG記載例

【NG表現の例】
×・・・「目を離したすきに」「不注意で」
×・・・「以後十分注意します」「今後は気を抜かないようにする」
上記のような報告では、ミスの原因は注意を怠った「人のせい」になっています。ヒューマンエラーを100%なくすことはできないので、この考え方では繰り返しミスが起き続けます。だれかのせいにするのではなく「組織としてエラーが起きにくい環境や仕組み」を検討し、それを報告書に明記していきましょう。
事故報告書は誰が書く?
介護の事故報告書は、基本的に事故を発見した人が書きます。事故当時の詳細は当事者でなくては分からないため、事故を発見したら記憶が新しいうちにメモを残すなどして、正確に記入しましょう。
もちろん発見者一人ですべての項目は書けません。引き継いだ人に事故後の状況を確認したり、分からないことがあればその時の現場リーダーなど責任者に聞きながら記入していきましょう。
とくに書事故報告書の後半、「事故の原因分析」と「再発防止策」については、さまざまな角度から検討する必要があります。一人で書くのではなく、ほかの職員や多職種と協議し、その結果をまとめて責任者の確認をとるようにしていきましょう。
事故報告書を前向きに活用しよう

事故報告書を書く理由は、「原因を分析し、再発防止策を検討する」ため。決して本人に反省させるためや、謝罪、言い訳といった後ろ向きな理由で書くわけではありません。
市町村への報告義務がないケースでも、なにかアクシデントがあれば作成し、再発防止につなげていきましょう。こうしておけば後になって症状が出た場合でも、さかのぼって事実確認ができるため、治療に役立ったりトラブルを回避する証拠になったりします。
介護事故のリスクを減らすヒントが詰まった事故報告書を、ぜひ前向きに活用していってくださいね。